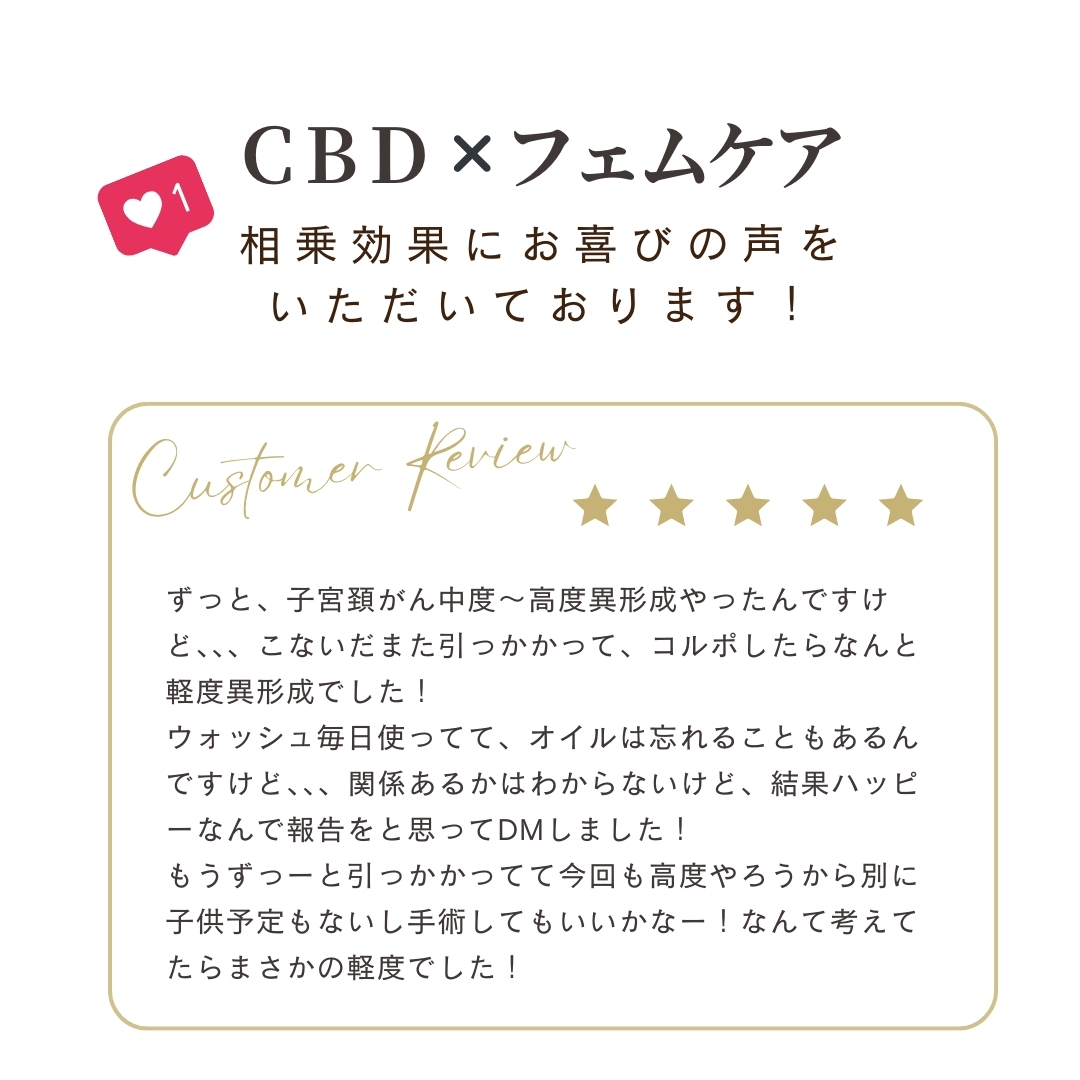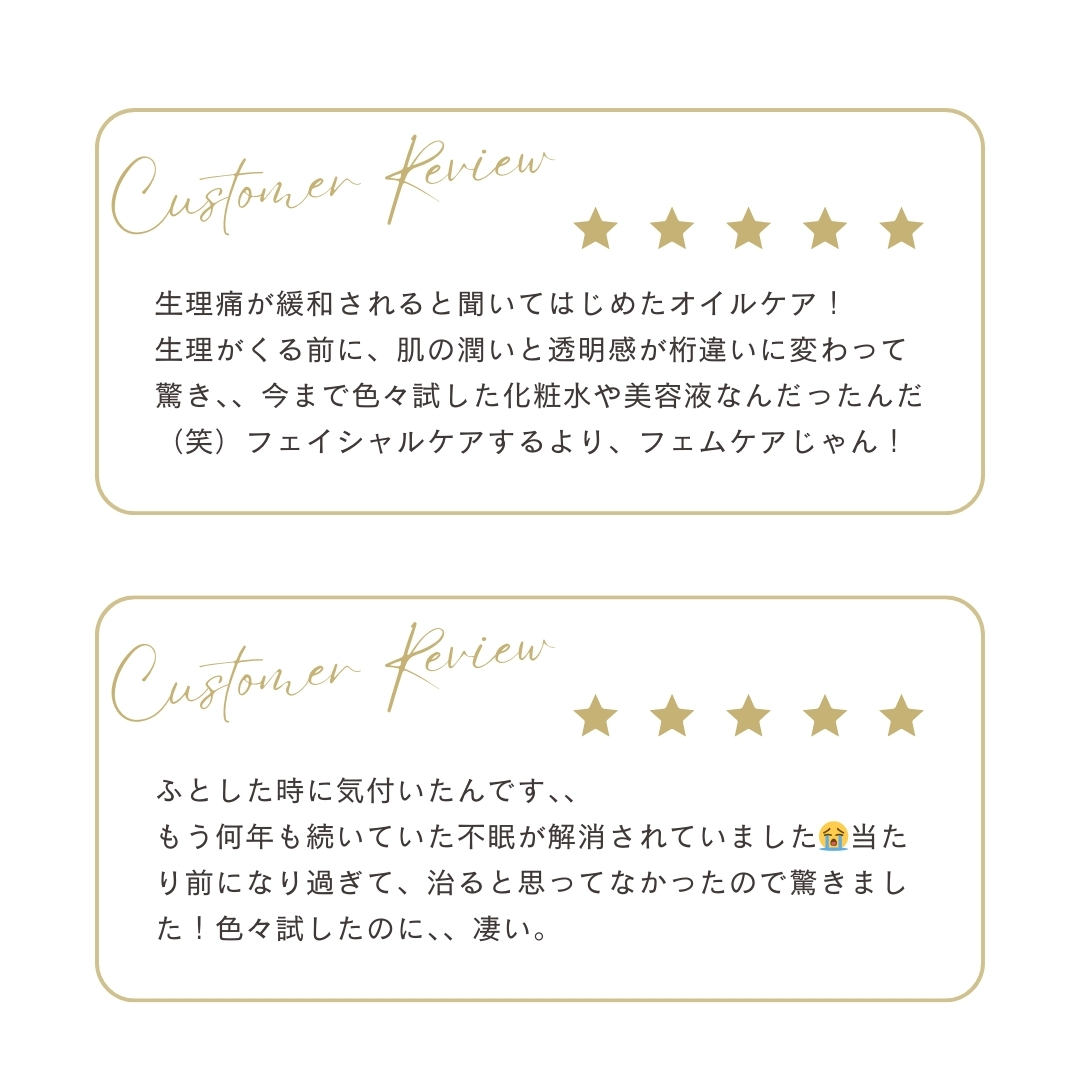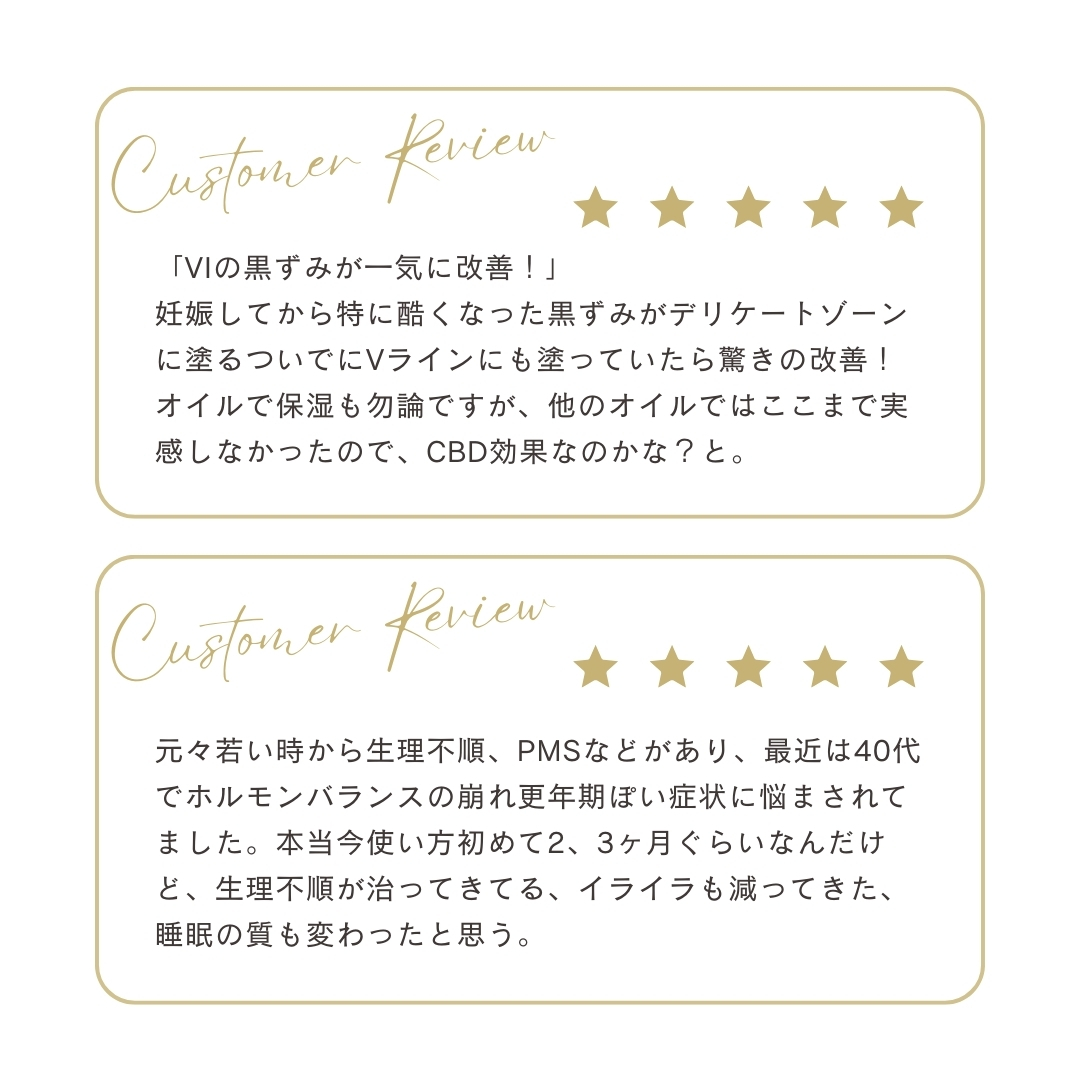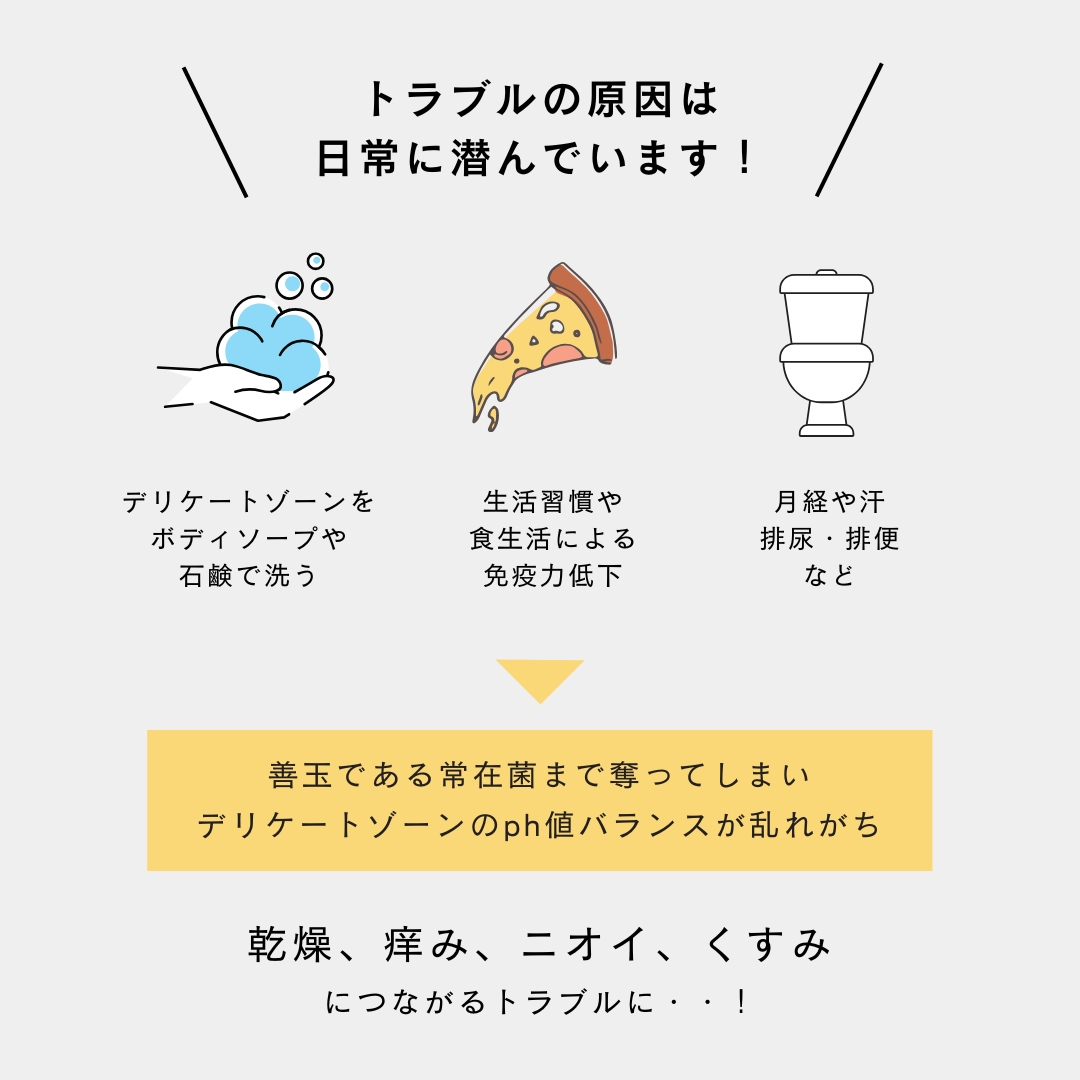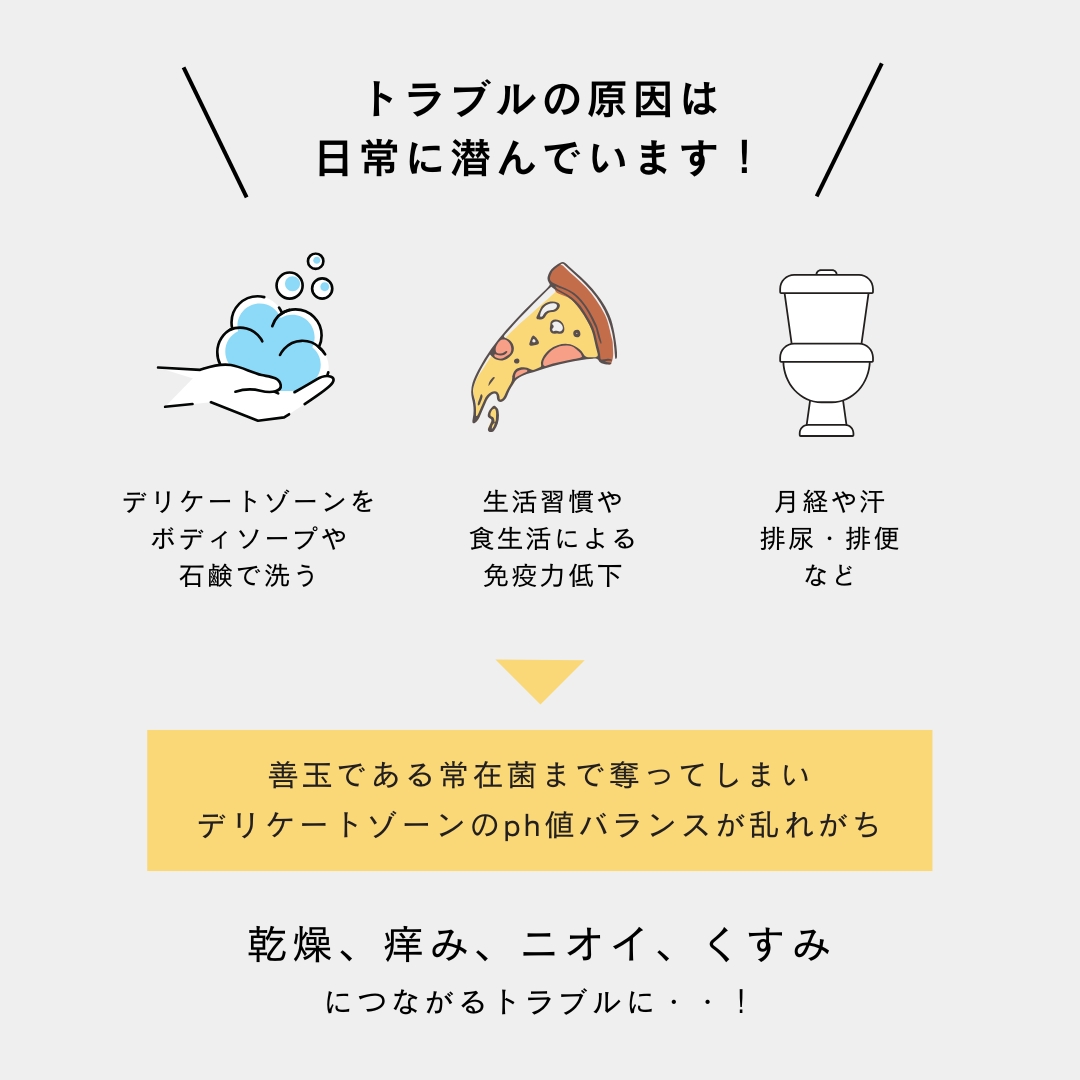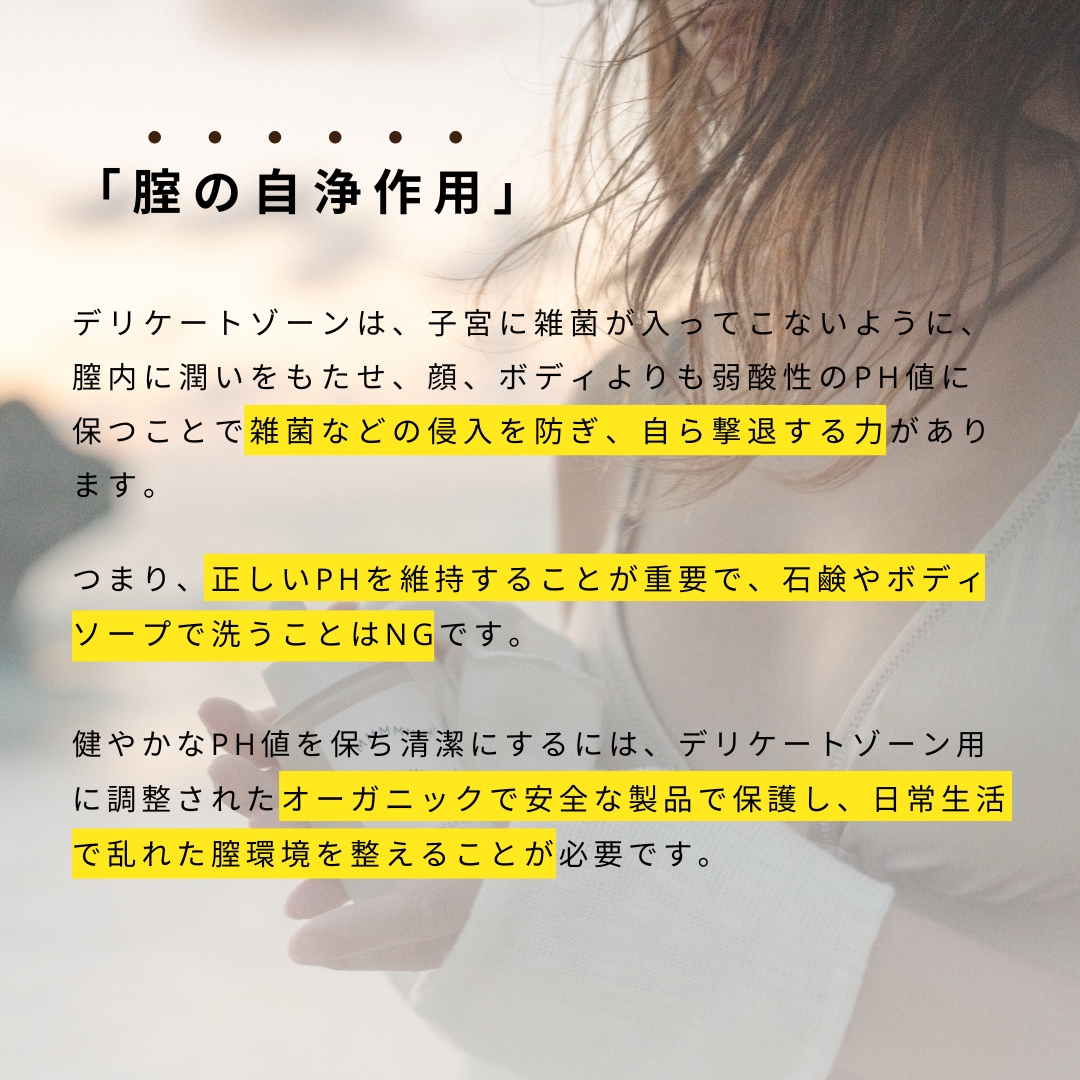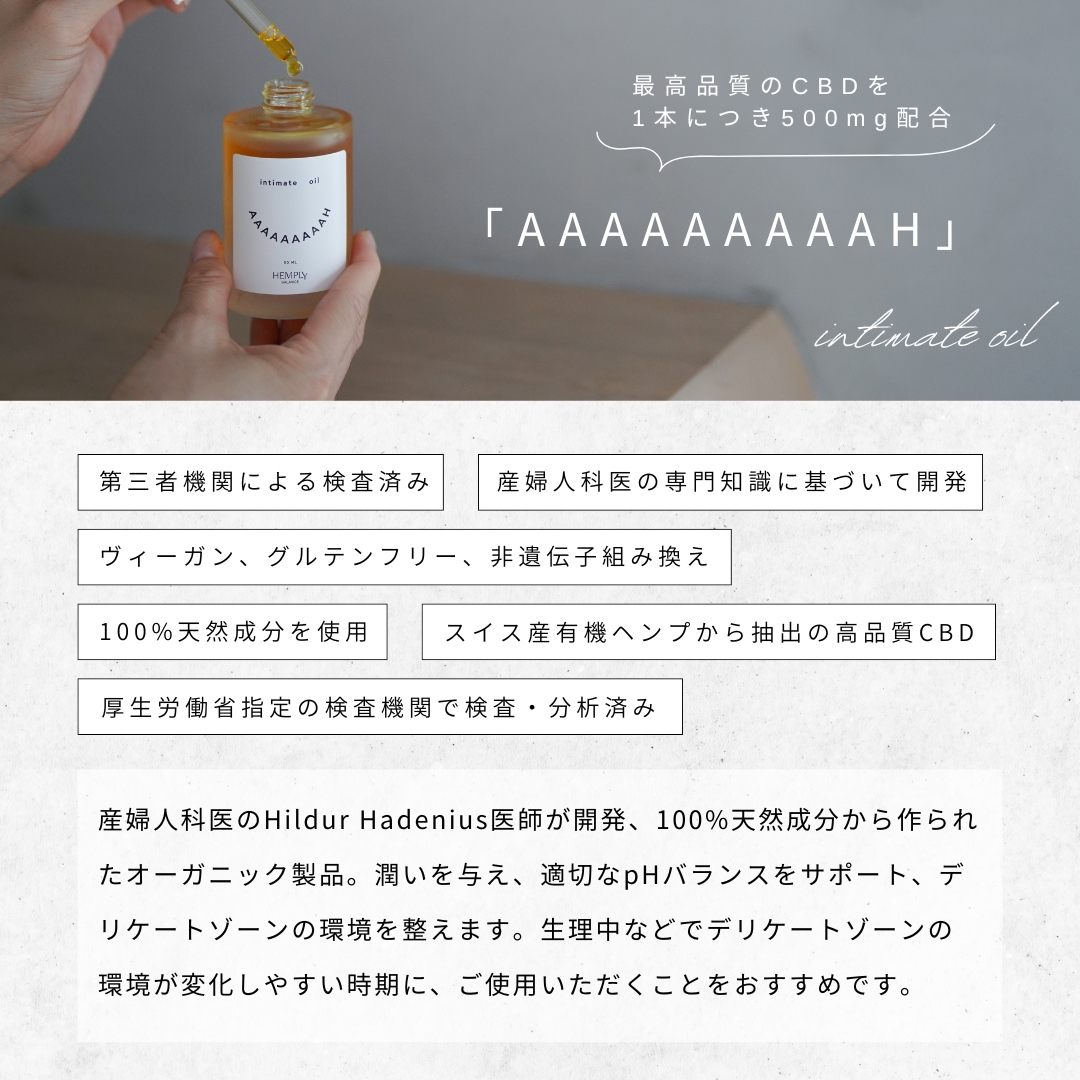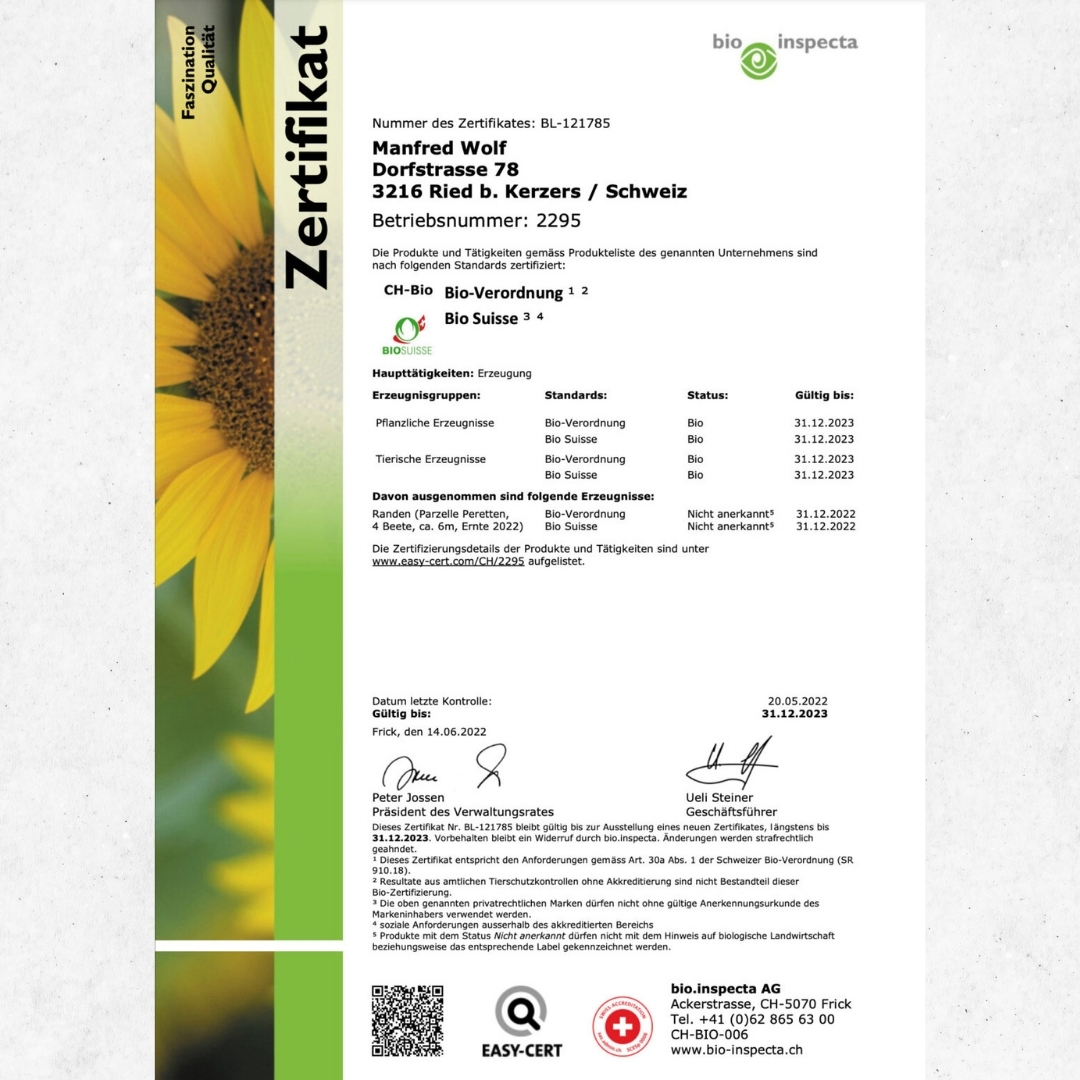こんにちは、フェムケアコンシェルジュの木川誠子です。
先日、本屋で“脳を癒す”というキーワードが目に入ってきました。現代人は、パソコンやスマートフォンなど、デジタルデバイスが日常的なツールになっていることもあり、脳に刺激を与え続けている状態といえます。だからこそ、脳を癒すという視点は必要。
女性ホルモンを知る

Photo by Maxim Bogdanov on Unsplash
私自身、フェムケアは女性ホルモンを意識した健康習慣だと考えています。ということは、女性ホルモンが正常に分泌されていることはとても大事です。
女性ホルモンには、エストロゲンとプロゲステロンの2種類があります。エストロゲンは妊娠の準備のため、プロゲステロンは妊娠を維持するためというように、女性ホルモンは妊娠のためにあるホルモンです。そのため、生理周期にあわせて分泌バランスが変化しています。
生理期間が終わるとエストロゲンの分泌量が増え、排卵後から生理前にはプロゲステロンが増える時期。このような女性ホルモンの分泌バランスの変化は、肌やメンタルなども影響を与えています。例えば、エストロゲンは、肌にうるおいを与えてくれ、新陳代謝も高まるので、体型管理をするならこの時期。一方、プロゲステロンは、身体に水分を溜めようとするためむくみやすくなり、食欲も旺盛に。生理前に気持ちが落ち込みやすくなるのも、プロゲステロンが要因のひとつとされています。
さらには、年齢によっても女性ホルモンの分泌バランスは変化していきます。心身ともにうれしい作用をもたらしてくれるエストロゲンは28~30歳頃がピークとされ、以降は徐々に分泌量が減っていきます。閉経を迎える50歳前後には、ほぼ分泌されていないのが現実。
女性ホルモンは自律神経にも関係している
女性ホルモンは脳からの指令で分泌されており、視床下部と脳下垂体という機関が司っています。具体的には、視床下部からエストロゲンの分泌命令が出されると、脳下垂体に指令を伝えるためのホルモンが分泌されます。そのホルモンが卵巣に伝わると、エストロゲンが分泌され、指令通りに行われたかフィードバックされるまでが一連の流れ。分泌命令からフィードバックまでが正常に行われることが重要になります。
ただ、疲れやストレス、過度なダイエットなどで、この一連の流れがバグってしまうことがあります。その理由は、分泌命令を出している視床下部が、自律神経の中枢も担っているからです。
視床下部は脳の中心部に位置する小さな組織ですが、たくさんの神経核から構成されているため、体温調整や睡眠、ストレスの応答、摂食行動などの生理機能を管理しています。例えば、ダイエットを頑張りすぎてしまうと生理が止まることがあります。それは視床下部が担っている生理機能の調子が乱れてしまい、身体を守るための反応のひとつとして生理を止めています。また、更年期を迎えると、ホットフラッシュや気分の浮き沈みなどの症状が現れることがあります。この場合は、エストロゲンの分泌量を増やそうとして指令を出していても、加齢による影響で卵巣機能が衰えてしまうことによって応えられないために起きていると言われています。
頭頂部のツボで脳を癒す

Photo by Anna Keibalo on Unsplash
生活習慣や加齢など、さまざまな要因で女性ホルモンが正常に分泌されなくなるため、ケア習慣を身につけることが大切です。趣味に没頭する、睡眠の1時間前からデジタルデバイスを触らないようにする、CBDオイルを取り入れるなど、さまざまな方法がありますが、ストレスを感じた時は脳にも影響が出ているので、頭の疲れをリリースすることも意識してみてください。
頭頂部には百会(ひゃくえ)と呼ばれるツボがあります。両耳の延長上、頭のてっぺんの少しくぼんだようになっているところです。この部分を、親指の腹を使って、心地いいと感じる程度に深呼吸をしながらプッシュ。
百会の刺激で期待されること
・頭痛や肩こり、目の疲れなどの緩和
・自律神経の働きを整えてくれる
・ストレスリリース
・睡眠の質を安定させる
など
親指の腹にCBDオイルを塗布して、百会に塗り込むようにプッシュするのもおすすめです。ツボはピンポイントではなく、その周辺を含めて刺激できていればOK!デスクワークしながらでも、トイレのついでに……でも、手軽にケアできる方法なので、ぜひ試してみてください。
(プロフィール)
フェムケアコンシェルジュ 木川誠子
出版社勤務を経て2009年よりライター・エディターのフリーランスとして活動。ウェルネスや美容、ライフスタイルのコンテンツを発案し、ディレクションから執筆まで一貫して携わる。2016年から兼ねてより関心のあったフェムテック領域に本格的に取り組み始め、フェムケアをはじめ、五感を通して自分を知るための”フェムアートプロジェクト”を立ち上げる。2022年には『株式会社k company』を設立し、その実践の場を創造・提供。また、10年以上の取材による知見と3000個以上のフェムケア製品を試した経験を活かしてメディア出演やセミナー講師など、多岐に渡って活動中。https://kcmpny.com/